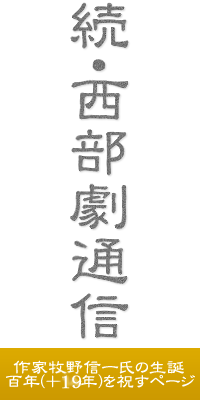更新履歴
■2013/1/7 サイト化粧直し開始いたしました。
■2010年開催朗読会
4月10日『天狗洞食客記』朗読会案内PDF(終了)
■2009年開催朗読会
6月27日『月あかり』朗読会案内PDF(終了)
■2008年開催朗読会
9月21日『ゼーロン』朗読会案内PDF(終了)
7月27日『心象風景』朗読会案内PDF(終了)
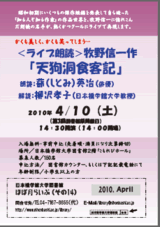
■朗読者、蔀英治氏のインタビュー『マキノを音声で伝える快楽、聞く快楽』(05/03/18)

関連ページ:『牧野信一の文学』刊行(近田茂芳著・夢工房)
(告)2004年8月29日、種村季弘先生が逝去されました。直ちには何の言葉も吐けませんが、慎んで哀悼の意を表します。
保昌正夫 旺文社文庫『鬼涙村 他十一編』(昭和39年)解説から
父の渡米に関連して(「文学的自叙伝」解説より)
牧野の父久雄は、信一の生まれた翌年(明治三十年=一八九七年)、単身、アメリカへ渡ってしまっている。信一の生まれた小田原のあたりは、当時、移民熱、渡米熱がさかんであったようだが、それにしても長男が生まれてすぐにアメリカに出かけてしまうというのは、どうもナミでない気がする。父親でありながら、家に落ち着いていられない、どこかボヘミヤンタイプのところがあったということだろうか。このボヘミヤンというのは、俗世間のとりきめ、しきたりなどを無視して、自由、奔放な生活を送る人、といった意味だが、牧野信一にも、このボヘミヤン気質は遺伝した。牧野信一の文学はバガボンド、さすらいびとの文学であり、その意味から一種の無頼派の文学ともみられるのである。 ↑先頭へ
「村のストア派」解説より
ストア派というのは、ギリシャ哲学の一派で、禁欲、克己を旨とし、平静な心境が唯一の幸福と説く。およそここにいる樽野とは逆の主張、立場であるが、樽野は「喋り続け」、ひたすら饒舌であることで、換言すれば、じれったさムキ出しであることで、独自の、逆行のストイシズムを打ちたてようとしている。「哲学者の門をラマンチアのドン・キホーテ的情熱で振り仰ぎながら」「喋り続け」ようとするのである。牧野の逆説的「ロマンティック・スピリット」のあらたな開花、ひいてはプロレタリア文学の進出の応じる芸術派の立場からの主張が、ここにみられることになろう。そして、ここには牧野信一バンドの音楽も鳴っているようである。 ↑先頭へ
「吊籠と月光と」「西部劇通信」解説より
「西部劇通信」の「西部」にも、小田原近在の田園、村々が、それに「見立て」られている。そしてこの「通信」には、どこか時世諷刺も読み取れるようである。「ギンブラ」「思想善導」「総選挙」(この年おこなわれ、「民政党」が第一党となった)などに対する-。これらは牧野の芸ともみられようが、自在の筆致はやはりそこにも冴えている。牧野独立プロつくるところの小活動劇の秀作である。 ↑先頭へ
「ゼーロン」解説より
[ゼーロン」は「更に私は新しい原始生活に向かうために」と書き出される。この書き出しには、現実生活を蹴とばして、の思いがこめられているだろう。しかし、蹴とばすことで、むしろ幽遠な、しかもがっしりとした現実が、牧野の意識を介して、立ち現われてくるのである。当時の文芸時評に若い批評家であった河上徹太郎は、その辺のところについて、つぎのように叙べている。
(河上徹太郎引用-略-)
そうだ、ここには「作者の自意識」を介して「影像の現実」が写し出されている。いってみれば、現実以上の現実、日常の現実よりはさらに「襞の細かい現実」が織り出されているのだ。また「私」の姿が、「比喩ではなくて象徴だ」というのは、ここに出てくる「私」が、類型でなくて典型だ、ということでもあるだろう。「内面的曝露に耐え得る美しい魂」の持ち主というのも、牧野の小説が単なる私小説ではなくて、独自の「私」小説になっているということだろう。 以前、人文書院版の『牧野信一全集』が編まれるのを手伝ったとき、この作品の背景となった辺りを歩いてみたら、目の前の風景がこの小説そっくりなので、びっくりした憶えがある。小説が現実を模倣しているのではなくて、現実の方が小説を模倣しているとみえたのだ。牧野の小説は現実以上に真実だな、とあらためて感じ入ったのである。 ゼーロンは「Z」などの名で牧野のほかの小説にもあらわれて、「ゼーロンもの」と呼ばれる騎馬小説を形づくってもいるが、やはりこの「ゼーロン」が牧野のアドベンチャーシリーズの頂点的作品だろう。 ↑先頭へ
「サクラの花びら」解説より(一)
牧野信一は小田原と東京の間を往き来したほかには、ほとんど自分の知り合いの住む土地を訪ねる(それも関東一円にかぎられる)ほどの、旅とはいえないほどの旅しかしたことがない。その行動範囲はきわめて狭いのであるが、それでいて、作品のフィールドとなると、ギリシャの昔に発して、古今の範囲も、東西の範囲もすこぶる広い。牧野は父親を通じてアメリカを夢みたにすぎないのだが、「サクラの花びら」などは、この時期、これだけにアメリカを描いた小説はなかっただろうと思われる。牧野は夢みることで、そこへ、-そのときのその場へ翔んで行ってしまうのである。「サクラの花びら」の場合は、吾が父がそこにいたから翔べたのである。
「サクラの花びら」解説より(ニ)
実はこの小説は朝日新聞に載せるために書いた試作品だったらしい。作品としては一部分であり、未完である。このままでは新聞小説としても通用しないだろう。それにもともと牧野は大衆向きの小説、まして新聞連載などは上手くやれる作家ではない。
しかし、「サクラの花びら」は牧野にとって賭けた作品であったのだろう。「病弱者、遊蕩児」ではなく、「戦人としての望み」を託したものであったこれまでの風流旅行(センチメンタルジャーニー)風の手法ではなく、意気ごみをこめた、アメリカに在りし吾が父の像を、ここで示そうとした。それに身をもって当たることで自分をも立て直そうとし、自分のよみがえりをはかったのである。ギリシャ牧野にかわるアメリカン牧野が、ここに出現している。これが牧野が最後の力を振りしぼった、起死回生を願った作であった。牧野は錨を揚げようとして、揚げきれなかったのであろうか。 ↑先頭へ
牧野信一の死について
牧野信一が逝った昭和十一年という年は、いわゆる皇道派の青年将校らによるクーデター、二・二六事件のあった年で、昭和の時代にも大きな転換があらわれてきた時期である。牧野の死はその直後で、そのとき寄せられた追悼記にも、牧野の死が文学者の死で、同時に時代の死であるとみているものもある。昭和二年の芥川龍之介の死に見合うようなところもあったのである。作家として、牧野のような生き方、書き方をしてきたものが、「衝動的」にもせよ、押し込められ、突き落とされしてゆくことになったのである。自殺を自尽ともいうが、自ら尽き、自らを尽くした感があったのである。 ↑先頭へ
以上
保昌正夫先生のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。(編集部)