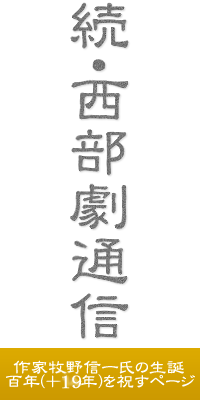牧野信一と小田原
牧野信一の前に、もしも故郷小田原とそれを囲む足柄の山々がなかったとすれば、「ギリシャ牧野」と呼ばれたあの特異な牧野文学の世界も、生まれなかっただろうと思う。
彼はいわば引越し魔で、東京においても幾つ転居を繰り返したか分からないほどだが、小田原にも何度も帰っている。ただし帰郷――特に長期にわたる帰郷――の大半は、故郷や父母を懐かしんで、などというかわいいものではなく、東京での生活に行き詰った挙句の逃避行だった可能性が大きい。
牧野青年が初めて小田原を離れたのは、大正三年の春。小田原中学を出て、早稲田大学に進む。卒業後は時事新報社の少年雑誌記者となり、やがて結婚。在学中からぽつぽつ書いていた小説も、少しずつ認められ始め、と、いかにも順風満帆に見えるのだが、大正十年末か翌年始めころ、身重の妻を連れて小田原に戻ってしまう。神経衰弱気味だったとも言われるが、理由はよく分からない。当時の牧野家は――牧野の〈小説〉を信じるならだが――父の事業熱と放蕩で崩壊寸前であり、妻子を連れた居候としては居にくかっただろうし、小説「熱海へ」でそんな家庭状況をすっぱ抜いた手前、余計に居にくくもあったろう。加えて当時の牧野にはほとんど収入もなく、おそらく母からの援助だけで暮らしていたと思われる生活は、なんとも不本意な日々だったのではなかろうか。
当時を描いた小説「スプリングコート」の末尾近くには、「その後彼は東京に来て、或る新聞社の社会部記者となつて華々しい活動を始めた。間もなく彼は、その非凡な手腕を同僚に認められて、社から大いに重要視された」とある。この文章の背景には、執筆の少し前、中戸川吉二から雑誌『随筆』記者として東京に招かれ、多くの文士連の知己を得たという牧野の現実が見える。「非凡な手腕」はちょっと言い過ぎだろうが、東京へ出て社会の一線で働くことが、〈成功〉の象徴であるような書きぶりであり、出世作となった「父を売る子」もこの記者時代に書かれている。ただしその内容は小田原での逼塞生活である。皮肉な見方をすれば、これらの父母小説も、小田原帰郷がなければ生まれなかったわけだ。
しかし、小田原が牧野文学にもたらした最大の功績は、昭和元年末あたりから四年以上に及ぶ長期滞在時にあったと言えるだろう。この帰郷も『随筆』の終刊と、痔疾や神経衰弱の悪化が原因かと思われ、貧乏生活も相変わらずだったろうが、彼の周りに集まった人々との交流が、牧野文学を変えるきっかけを作ったのではあるまいか。例えば福田正夫のような、直前に小田原を去った北原白秋周辺にいた人々や、川崎長太郎、彫刻家の牧雅雄、画家の朝井閑右衛門、等々。彼らと共に、小説「心象風景」に描かれたような飲み会が、毎日繰り返されていたらしいし、山田村村長と知り合ったことなどから、足柄地方へ足を延ばす機会も増えたのではないか。
現実の牧野は、山田村(大井町)へ行くにはオートバイを飛ばしていたというが、牧野文学では、それは騎馬行になる。村の居酒屋はアウエルバッハに変わり、祭りの大太鼓はガスコンのバラルダに変ずる。現実から虚構へのひと飛びだが、この間に横たわる溝は、非常に大きい。それを後押ししてくれたのが、小田原での生活だったと思うのである。