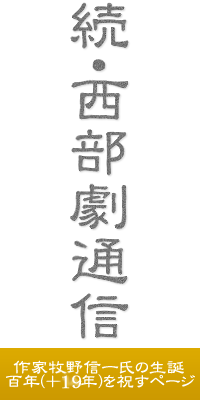私と牧野信一との出会い
私が牧野信一という作家と出会ったのは大学三年時、教育実習中に読んでいた短編集がきっかけであった。当時読んだ作品は「風媒結婚」。この作品はその後の研究発表会でも取り扱った個人的に思い入れの深い作品である。
「牧野信一という作家を見つけてきたことがまずは評価されるべきだと思う」この言葉は中間発表会に先立って行われた近代文学ゼミにて大学院生の方から頂いた。私自身も初めて耳にした作家だったし、当時は先行研究が少なかったこともあり、自身の見解を述べやすいのではないかという単純な理由で牧野を研究し始めた。
牧野信一という作家は近代という多くの優れた作家を生み出した時代において何故か同時代の谷崎や横光利一などに比べると、先行研究も少なく作品に対する論考もかなりの余地が残されている。ここで問題になることは作家に対する文学的価値をどのように決定するのかということである。牧野は自身の「爪」という作品を島崎藤村に賞賛されてから文壇に登場する。それ以降も意欲的に作家としての活動を行っていた。初期・中期・後期という時期の中で作風を変化させながら「父を売る子」「ゼーロン」「鬼涙村」など優れた(と私が考えているだけかもしれないが)作品を多く残してきた。にも関わらず何故彼に対して、また彼自身の作品に対して研究が進んでいないのか、その理由がやはり文学的価値、つまり評価にあると私は思うのである。
牧野に対する評価はどうしても私小説的見方に支配される傾向がある。彼の家庭環境、父親が海外で働いている状況、故郷など作品に登場する様々な要素が彼の人生と結びつけられる傾向がどうしても強いように私には思われるのである。私小説というものはあくまで小説の一形態に過ぎず、ある作品を私小説的だと考えるのは読者の価値判断によるものである。たとえ、作家自身が「これは私の実生活を反映したものだ」と表明したとしても、文学というものが言葉を用いて表現されるものである以上、それは虚構性を帯びることになるのである。であるならば、やはり作家が残したテクストを一つ一つ丁寧に見ていくことが必要なのではないだろうか。どれだけ彼の残した作品世界が彼の実生活に拠っているかどうかを追求したところで、そこからどれだけの価値が見出し得るのであろうか。むしろ、私小説的という色眼鏡を外し、彼が彼なりの見方で描いた作品の世界というものを彼が残したテクストを追っていくことで追体験することが必要ではないだろうか。
私の卒業論文はそのような問題意識から出発した。牧野の中期作品の中でも主人公の呼称という観点から作品を分類し、「樽野」という主人公が登場する一連の作品群を対象にテクスト分析を行った。作品分析を進めていく中で確かに感じたことがある。それは「牧野は言葉の使い方というものに対して非常に意識的であった」ということである。彼の作品は、確かにギリシャ神話に典拠を見出すことのできるものもある。しかし、一人の作家が膨大な言語表現の蓄積の中から意図的に選び出した言葉の集合体であるテクストを「ギリシャ神話的な要素」という言葉で片付けるのは非常に早計だと私は思うのである。私の論文で論じている事を使うならば「同一人物に対する複数の呼称」や「肩書きの問題」、「時間感覚のズレ」が主なものであるが、これらは今までの作品論やテクスト分析では指摘されてこなかったものである。もちろん一人の大学生が行ったものであるし、分析の正確さなどに問題がある可能性は否定できない。だが、私がここで伝えたい事は自身の論考の正確さではなく、牧野信一のテクストを再読する事の重要性である。牧野のテクストは私に「読む」ということがどういうことかを再認識させてくれた。これから彼のテクストに触れる方、今まで触れてきた方もきっと実感される(あるいはされた)ことだと思う。
私はこれから高校の教員として子供達と学んでゆく。教員になる前に、牧野という人物に出会い、埋もれていた彼の作品を掘り出すことができたということ。そして今まで指摘されてこなかった、私が考える彼の作品の魅力というものを感じることができたという経験は何事にも変えがたい経験であると思う。教員になった後でも、牧野の作品を読む事は止めないし、彼について未発見の価値や魅力というものについて考えていきたい。
最後に今回、私のような若輩者にエッセイ執筆という依頼を頂いた熊谷真理人氏に心からお礼を申し上げる。また、このエッセイを読み、一人でも牧野信一という作家を知り、読む人が増えればこの上ない喜びである。
中田晃平(なかた こうへい)
佐賀県出身。大分県立大分雄城台高等学校卒業後、広島大学文学部に入学。
近代文学を専攻し、大学三年の夏に牧野信一と出会う。
卒業後は高等学校国語科の教員として勤務する。